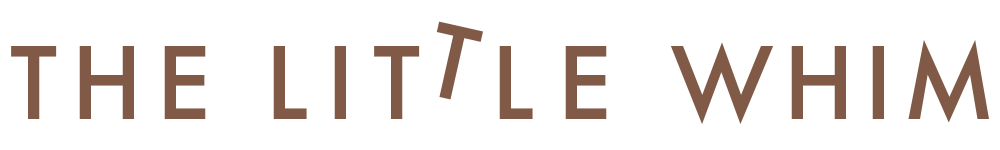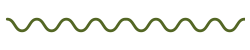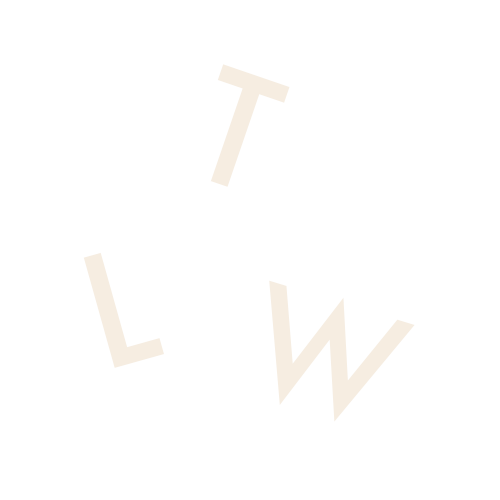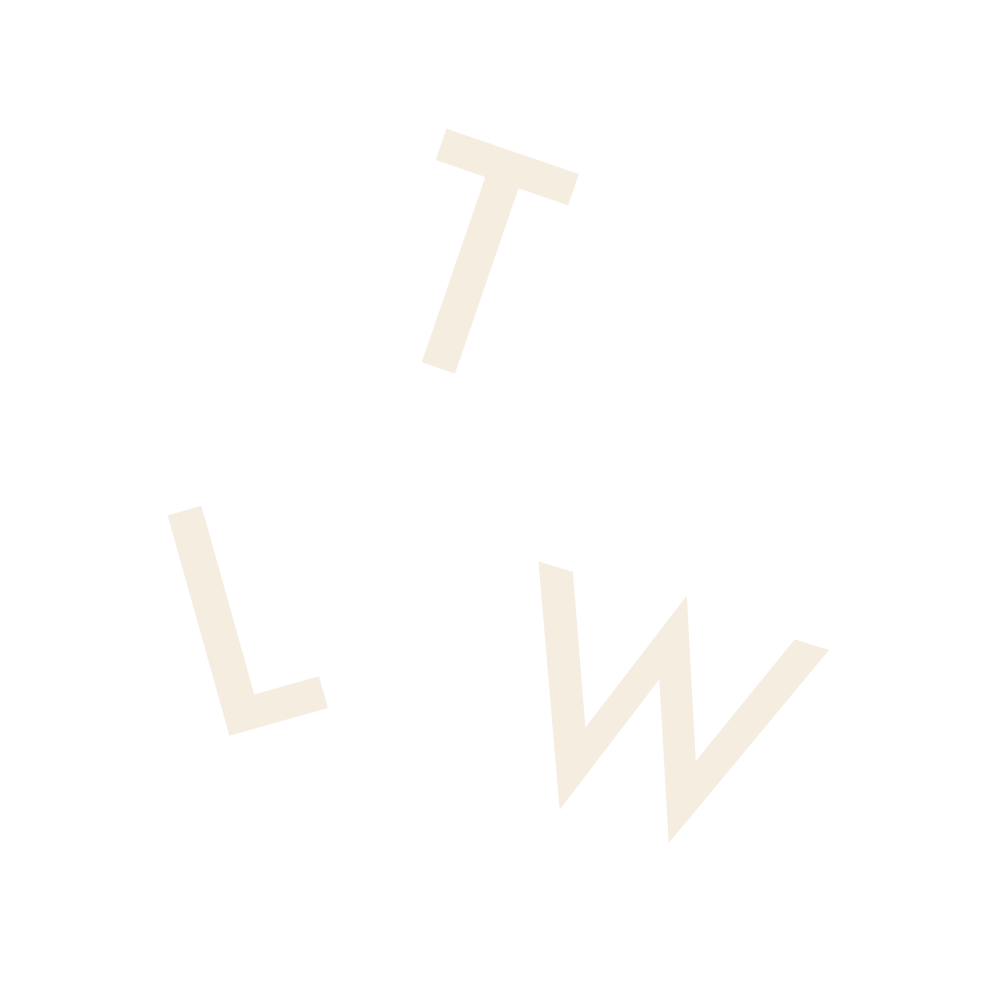すこし変なタイトル「温又柔さんを知って」には、わけがある。
ニューヨークに住む私には日本語の本は手に入りにくい。すこし前にやっと、温又柔さんによる「来福の家」という、中編小説が2編入った一冊を隣の地区の図書館で見つけ、読むことができた。
しかし実は私は、作品を読む前からこの方にすごく惹かれていて、温さんの存在を知れたのがうれしい、というのがおおきいのだ… 物書きの方に対して、それは失礼なのかもしれないけれど。
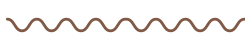
温さんを知ったきっかけは、おしゃべり。TBSラジオ「アシタノカレッジ」金曜日、武田砂鉄さんの番組内で、彼女がゲスト出演していた2022年10月22日の回。
温さんの語り口はどちらかといえばゆっくりで穏やか、だけれど明るくて、笑顔があふれるのが見えるよう。しかしその話す口調と言葉選びの奥にある話す内容は、とても力強くて…。
聴いているうちに、さして長くないトークにもかかわらず、この人の口調と言葉選びは、ものすごく長かったり深かったり強かったりする思いの蓄積があるからこそでは、と思えてくる。その思いは、必ずしも「正義!」などとしてどーんと出てくるものだけではなく、いろんな方向に広がっていくようにおおききかったり、何層にも重なるように複雑で、それを今まで何度も反芻してきたのかな、と。
気になって、彼女のことを検索した。インターネットで見つかるプロフィールとインタビューなどの内容を集めると、温さんは台湾で生まれ、3歳から、家族で引っ越してきた日本で暮らしている。日本語のネイティブであり、台湾人の両親は台湾語をまじえた中国語を話し、それらにも囲まれて育ったそうだ。小説は日本語で書く。
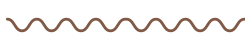
おしゃべりで知った作家の書きものを、やっと読めた。すると、「来福の家」収録の一作目で彼女のデビュー作である「好去好来歌」で綴られる文章は、温さんのおしゃべりとは違った。穏やかなのは同じだけれど、笑顔ではないと感じた。
主人公の楊縁珠は、きっと温さんの生い立ちに近い。「好去好来歌」は私小説と分類してもおおきくはずれてはいないと察する。主人公の日本語と中国語と台湾語の間での「揺れ」や「囚われ」が、親、祖父母などの代にもめぐり、家族がたどった歴史と現状をつなぎながら語られる。
台湾語も顔を出す中国語、そしてすこしの日本語をまじえて話す母の声が、まるで空気のなかで揺れたり流れたり浮いたり溶け込んでいくのを、日本語がおもな言語である主人公がつかまえ、言葉として飲み込んでいくように理解しているのかな、という様の描写はすごく好きだった。
窓の隙間から夜風が吹き込み、カーテンを静かに揺らしていた。風は、乾かしたばかりの縁珠の髪もサラサラと揺らす。母の声も揺れていた。日本語と、中国語と、台湾語と、三つの言語が、母の声の中で、ひしめきあっていた。母の言葉。声と、意味とが、重なり合っている。声と、意味とを、重ねるための綴じ目。もつれる。縁珠は、瞬きをした。綴じ目が、もつれていく。綴じ目の向こうに、意味が、渦巻いていた。
「好去好来歌」 温又柔
こういった、文章として好きだなと思える箇所がたくさんあったのだけれども、しかしこの作品は、それだけではなかった。ギリギリした痛みもたくさん与えた。このシーンだって、美しい描写 — 好きだな、と思ったけれど、自分の親との会話に、言語が交差しているから生まれている「揺れ」「ひしめきあい」、そして瞬きひとつで「もつれていく」ほど脆い「綴じ目」を描いているわけだ。親との会話がこんがらがることは言語が違わない場合にもあるけれど、より圧倒的な距離をつくるのではないか。
日常でたびたび発生する葛藤が、小説のなかで描かれる。たとえば、主人公の母が話す言葉を主人公の日本の友人が理解しない場面に遭遇し、恥じるような気持ちになるエピソードは、その経験がない読み手にもすこしは想像が湧きやすい。
ほかにも…「中華民國」(ものすごくはしょって、台湾のこと)と記載され、数年ごとに台北在日経済文化代表処で更新する自分のパスポートと、日本の友人が持つ日本のパスポートの重みが、同じ日本に住む者同士なのに違うこと。自分のパスポートに記載されている名前は「YANG YUAN ZHU」で、日本で暮らす自分の名前である「ようえんじゅ」とは読みが違うこと。日本で知り合って間もない人びとに、「ようえんじゅ」と、フルネームで名前を呼ばれがちであること(日本の名を持つ人にはしないのに)。親の代は台湾語混じりの中国語を、祖父母の代は日本語を、台湾が経た異なる支配の歴史があるゆえに話していること。中国語を学ぶ恋人に、「日本人のくせに」とあたってしまうこと。
…そういった場面が積み重なり、かなしさを残しながら終わっていく小説だった。
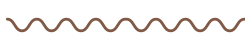
読後のギリギリとした痛みを、頭のなかで自分なりに整理してみようとした。なので、ここからは私の話も多くなる。
私は2013年にニューヨークに引っ越し、アメリカの永住者、移民一世の外国人だ。(幼い頃、一時的にだがそれなりの間、家族でイギリスに住んでいたこともある。)その一方で、この小説の舞台になっている日本では、その国の日本人。日本国内で異なるバックグラウンドを持つ人びとに向けられる圧力は、「国民性」とか「愛国心」などという言葉で表される「日本に住む日本人の結束」のようなものの裏にあることに、いつしか気づくようになった。日本各地での差別やヘイトスピーチ、そこから発展した悲惨な事件のニュースも見てきた。
「日本に住む日本人の結束」は同時に、今では日本のそとに住む私にも影響する。日本に住む日本人こそが日本人であるという考えに基づき(いや、そうなのかよくわからないけれど)、在外日本人には不便が多い。ましてや二重国籍など、私が生きている間に認められることはないだろうとくくっている。自分の持つ菊の紋章がついたパスポートが重くなる状況と、軽くなる状況があり、そのどちらにも痛みがあるのを、すくなからず知っている。
言語や言葉における痛みも、ある。まずは、外国人である自分を考えた際。英語はあとから身につけたもので、仕事で交渉ができるほどに言葉をつかえるレベルではあるとはいえ、今でもわからないことはままある。私は自分を、日本語と英語のバイリンガルとは言えるか自信がない。2つの言語をあわせて1.80リンガルくらいかな、と思っている。
そしてそれは日本語1.00、英語0.80というわけではない。いわゆる母語である私の日本語は、0.95くらいで、しかもその数値は落ちているのを感じる。日本との距離がどんどんひらき、そして私と日本を結びつける言語である日本語もその言葉も、曖昧になっていく。(これは、石沢麻依さんの「貝に続く場所にて」という小説に影響され、思うようになったこと。)
そしてそれ以上に、やはりこの小説の設定である日本で、日本人でない人びとが言語や言葉を通して経験することについて、思いをめぐらせた。「好去好来歌」で描かれる、日本に移住した主人公と、そのときどきのそととうちからの支配から日本語と中国語に強制された2つの異なる過去を経て今に至っているその家族。それぞれの言語が異なる状況は、台湾にルーツを持つ方々に与えた影響に責を負う日本の出身者である私にとって、さらにひずみを帯びたような苦しさを残す。やりきれなさが、恥や怒りとしてかえってくるのを、止めることはできない。
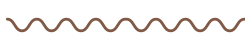
温さんが出演している、この動画も観た。「台湾生まれ 日本語育ち」というエッセイ集刊行の際に催された、作家・中島京子さんとの対談だった。
2人の会話のなかで、中島さんが、台湾文学史の本を読んで知ったことについて話していた。(その台湾文学史の編者は会話の中で「ちんさん」と触れられているのだけど、調べてみる限り、陳芳明さんのことだろうか。)
日本の台湾統治時代に日本語を強制され習得した台湾作家たちが、「抵抗文学」で日本の帝国主義に挑戦したり、日本のプロレタリア文学作家たちと協力した背景に触れたあとに続く内容である。
誰かに押し付けられたものであっても、言葉っていうのは、一旦その人が獲得してしまうと、もうそれはその人のものになって、その人が闘うための、その人が世界に対してなにか言うためのものにならざるを得ない。
(聞き取りを書き出したものであり、
漢字と句読点は THE LITTLE WHIM による)
中島さんの「ならざるを得ない」という言い方は、ここだけ読むとどこか違和感が残るかもしれない。しかし、会話の流れから読み取るに、たとえ強制された言語であっても、それをつかって闘おうとする人びとがいるのは当然で、それまでも奪うことはあってはならない、という意図からだったのだと思う。
温さんは、相槌の同意を添えていた。ちょうど植木に水やりをしながら、YouTube の番組を AirPods で聴いていた私も、窓際からキッチンに行き来する足が止まり、うなずきながら聴き入った。
台湾語に限った話ではないが、言語帝国主義の歴史から奪われたり縮小してしまった言語は、できる最大限の努力をもって今からでも回復・保全に努めることがまず第一に必要だ。その一方で、言語を奪われた人たちがあらたに(強要により)得た言語は、力になる。その人にとってのその言語で、表現し、伝えるための、力。日本語は、誰のものでもない。というか、誰かのためだけのものではない。得た人たち、これから得ようとしている人たち、みんなのものだ。
幼い頃日本に移り住み日本語を得た温さんは、作品を通して、そういうことを伝えようとしているのではないかな、と思う。彼女の書く内容が、日本の過去の暴力にも触れ、日本の日本人にとっては必ずしも心地がよくない内容になるかもしれなくても。
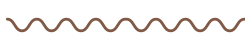
そんなことを考えながら、ニューヨークでは手に入りにくい温さんの本をほかにも読みたいな、とインターネットをうろうろしていた。すると、ショッキングな「騒動」(適切な表現がわからず、騒動と記しておきます)が、2017年にあったのを知った。
それは、第157回芥川賞で、温さんの「真ん中の子どもたち」が候補作となったときのこと。この小説は、出版社のサイトよると、「複数の国の間で自らの生き方を模索する若者たちの姿を描く青春小説」だそう。その際の選考委員の一人であった作家・宮本輝さんの選評が、物議を醸したそうだ。
当事者たちには深刻なアイデンティティと向き合うテーマかもしれないが、日本人の読み手にとっては対岸の火事であって、同調しにくい。なるほど、そういう問題も起こるのであろうという程度で、他人事を延々と読まされて退屈だった。
『文芸春秋』2017年9月特別号
私は「真ん中の子供たち」を読んでいないのでわからないことも多いのだけど、それでもこれは、ひどくショッキングだ。文学作品として「退屈」であるというのを、表現の手法や技術をもとに評するのであれば、それが文学評というものだろうから、理解する。しかし、この内容から読みとるに、宮本さんが「退屈」と評した理由は、テーマが日本人の読み手にとっては「対岸の火事」であり「同調しにくい」から、だ。すくなくとも、私にはそう読めるし、そう解釈するのは私だけではないと察する。
そもそも、文学って同調できるものを読むためだけなんですか?同調できないとだめなんですか?という話。特に、マイノリティ性を持つ作家がその視点から描く作品は、同じもしくは近い環境を共有するマイノリティ読者にとっておおきな意義があると同時に、それを知り得ないマジョリティ読者にも貴重な語りかけになる。作家であり文学賞選考委員である方が、さまざまな創作を評価するうえで、マイノリティ性からくる普遍性の欠如を「退屈」と評価するのは、ひどくズレていると思う。
でももっと深刻な問題は、その奥にある。「日本人の読み手」と、宮本さんが読者を独断的に限定していること。宮本さんが想定しているその「日本人の読み手」にとっては、これは「対岸の火事」で「同調しにくい」ゆえに「退屈」という判断を下していること(下せると思っていること)。「そういう問題も起こるのであろうという程度」の題材であると思っていること(思える自分の立場を理解していないこと)。たとえ「対岸の火事」であったとしても、ではその火を起こしたのは自分の国に関係する可能性を疎外していること。
むごい。。。
そしてこれは、ここでは温さん、つまりは作家へのむごさだけではない。この作品で描かれた状況に近い人びと、作品を読んで「同調」した人びと、ようは宮本さんが思うところの「対岸」にいる人びとに対しても、暴力的だ。文芸賞の選評で、どうしてこんな暴力を振るう必要があろう(選評に限らず、どこにも、そんな必要はないのだが)。
こういうことって、日常的にも起きる。
多様性!インクルージョン!いろんな人がいますよねはい理解してます、という風。しかし見せかけだけの多様性・インクルージョン達成の風は、違いを気にしないなり無視できるなりの状態でのみ吹く… 実際には違いがあるのに。だから、違いを気にしない・無視する時に、または逆に、気にしない・無視することが不可能なほどに違いが目の前で明らかな時に、とんでもなくむごいことを言う、する。意識的、無意識的にかかわらず。
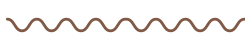
それは、アメリカでもある。特に人種・民族・文化・言語・宗教・ジェンダーとセクシュアリティなどが多様であるNYCのような街でもだ。またしても私のパーソナルな事象で、私に実際に起きたことになるのだけれど、自分のためのセラピーとして書き出したい。
フリーランスで昨年働いていたニューヨークのブランドは、日本のエージェントとも取引をしており、コロナ禍の厳しさも経験しながら友好なビジネス関係を保っていた。しかし円安が急激に進むと、それはガラリと一変した。急速かつ長引きそうな為替状況の変化というカネに直結する問題は、今までは看過できたお互いのコミュニケーションのちいさなズレがもたらす波紋を、以前よりおおきくした。
すると、ニューヨークのオフィスで、日本とビジネスをするうえでのむずかしさやストレスが話題にのぼる機会が増え、それは多方面に広がった。仕事のうえで必要な議題だったとは思う。しかし、偏見に当たるのか私は判断しかねたけれど、いくぶん極端に聞こえる意見もあった。アメリカ人中心のオフィスで唯一の日本出身者で日本人である私にとっては、居心地のいい状態ではなかった。
ある時、それをおそらく感じとったブランドのトップがとっさに、私に声をかけてきたのだけれど、その「思いやり」が、もっとも苦しい一言になった。いきなり投げかけられたあのフレーズ…… 「まぁでも、あなたはアメリカナイズされてるから。」(英語で言われた “But you know, you are Americanized, so.” を、ニュアンスを含めて訳)
まぁでも
あなたはアメリカナイズされてる
から
職場では仲が良かったとはいえ、友人のような親しさではなかったのに、私のなにを知っているの?アメリカナイズされていると私を判断しそれを私に伝えること、そして非パーソナルな話題から突然マイノリティに対してパーソナルな発言に切り替えることは、特に職場において適切かどうか、どうして考慮しなかったの?ブランドの責任者からそんなパーソナルなことを言われても、フリーランスである私は関係性から正直な返答はできず慎重にならざるを得ないだろうと、どうして考えなかったの?
しかしなによりこたえたのは、真ん中の「あなたはアメリカナイズされてる」の部分では実はない。「まぁでも… から」の方だ。まぁでも、私はアメリカナイズされてるから、なんなの?まぁでも、私はアメリカナイズされてるから、私を日本人だとは思っていないってこと?まぁでも、私はアメリカナイズされてるから、私は問題ないってこと?まぁでも… から、なんなの?
とっさの発言にも調子よく返すアメリカンな英語コミュニケーションを身につけるほど、アメリカナイズされていたかもしれない私(皮肉です)も、この時は文字通り絶句してしまった。思いやりだと思っているのかもしれないけれど、それは無知であり無関心であり非礼であるということを返したかった。けれど、感情が沸騰しそれは顔を真っ赤にし、すこし間をおいて、「そうは思わないな。」(“I don’t think so.”) と、「そう」(“so”) がなにを示すのか明確にきっと伝わっていないであろう返答を、なんとか口から出すのが精一杯だった。
日本語なら、もっとうまくこたえられたのだろうか… 今も考える。そのときの私の英語はきっと揺れていて、私が発した言葉は囚われていた。普段はもはやあまり意識することがない「外国で外国語を話す」自分が急に、自分の体からはなれた別人格として浮いたようにそこにはいて、とても無力で孤独だった。
(超複雑化したくはないのでカッコ書きにとどめるが、重要なポイントでもあるのは、その発言をした上司は実はアメリカ人ではないということ。ただ、移民であるそれぞれのアイデンティティを構成する要素はいろいろと違った。移民同士であっても、アメリカでの「アメリカンネス」を内在化し計量する傾向もある、ということだろう。)
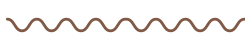
「好去好来歌」を読んだのは実はこれが起きたよりあとで、なのでことさら、この本のなかで描かれた日本とは違う場所で、私の気持ちははおおいに揺さぶられた。本のなかではマジョリティであり、それを移転させた私の実際の状態ではマイノリティである、その2つの読み方が、ページをめくりながら同時進行した。
偏見や差別、無知や無関心や無理解の話をする際に、「明日は我が身」というのはあまり的確な説得だとは思わない。
けれども、対岸だろうが自分の岸だろうが、どれだけ距離があろうが、自分や誰かの、偏見や差別、無知や無関心や無理解による火事は起きる。前述の、多様性!インクルージョン!いろんな人がいますよねはい理解してます、という風は、あまりに中途半端で、かえって炎の勢いを強めたり、飛び火を起こすかもしれない。そして、広がる海が接する岸は無数にあり、こっちとあっちという二元論ではとても語れない。
かなしさを残して終わった「好去好来歌」。主人公とその家族とともに、それぞれの時代と環境から、母語とは?母国語とは?外国語とは?と問う。言語と言語の間、もしくは言葉と言葉の間にある「揺れ」や「囚われ」を感じとり、言語や言葉がアイデンティティに与える影響を考えるにじゅうぶんな材料をくれた。温さんを知ることができ、このお話を読むことができて、よかった。
しかし、私たちの人生は物語ではなく、ページ数がどこまで続くかは、人生が終わるまでわからない。これまでと、今と、これからを生きていくうえで、私たちは言語や言葉をたくさんつかう。そこにある「揺れ」や「囚われ」の存在に私たちはもっと敏感であるべきことをあらためて確認したと、私は思っている。
最後にもうひとつ記しておく。この作品は小説(私小説)であり、温又柔さんは小説家である。この本で、日本の台湾ルーツの方々の生きる様を垣間見ることはできるが、台湾とそこにルーツを持つ人びとが経た歴史を体系的に理解するためのものではない。
私がその点についてこの作品からなにか理解できたことがあったとすれば、私には知るべきこと・学ぶべきことが途方に暮れるほどたくさんあるという事実に過ぎないだろう。そこには、たくさんのさまざまな書籍があり、たくさんのさまざまな人びとがいる。私たちは、今いる場所から今見えるものだけに凝りかたまらず、知ろうとし続けることができるのだ。