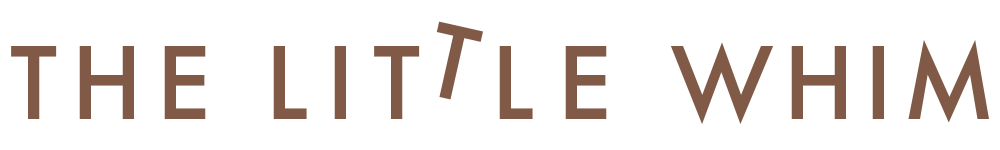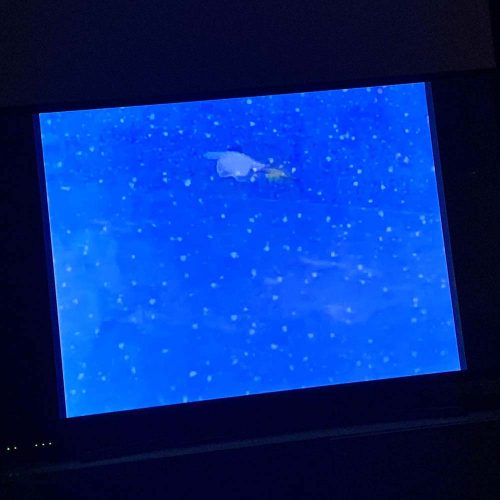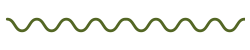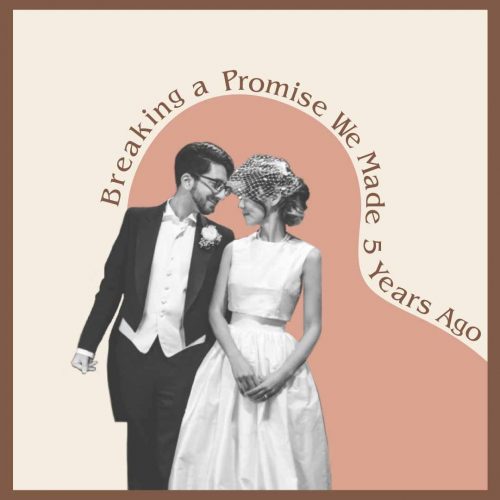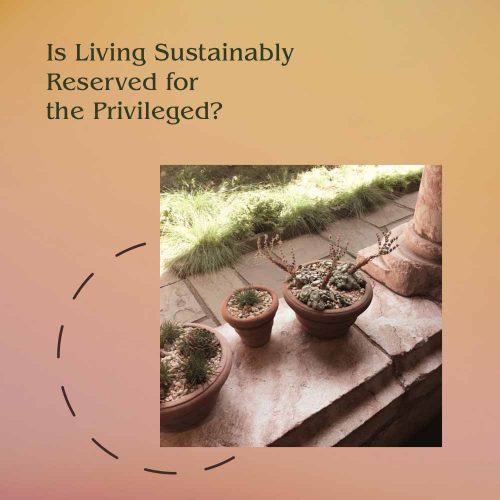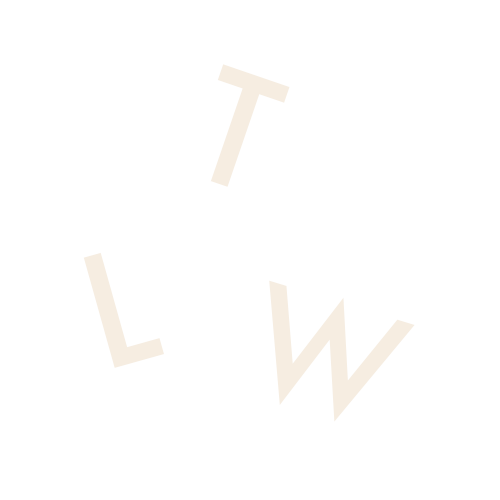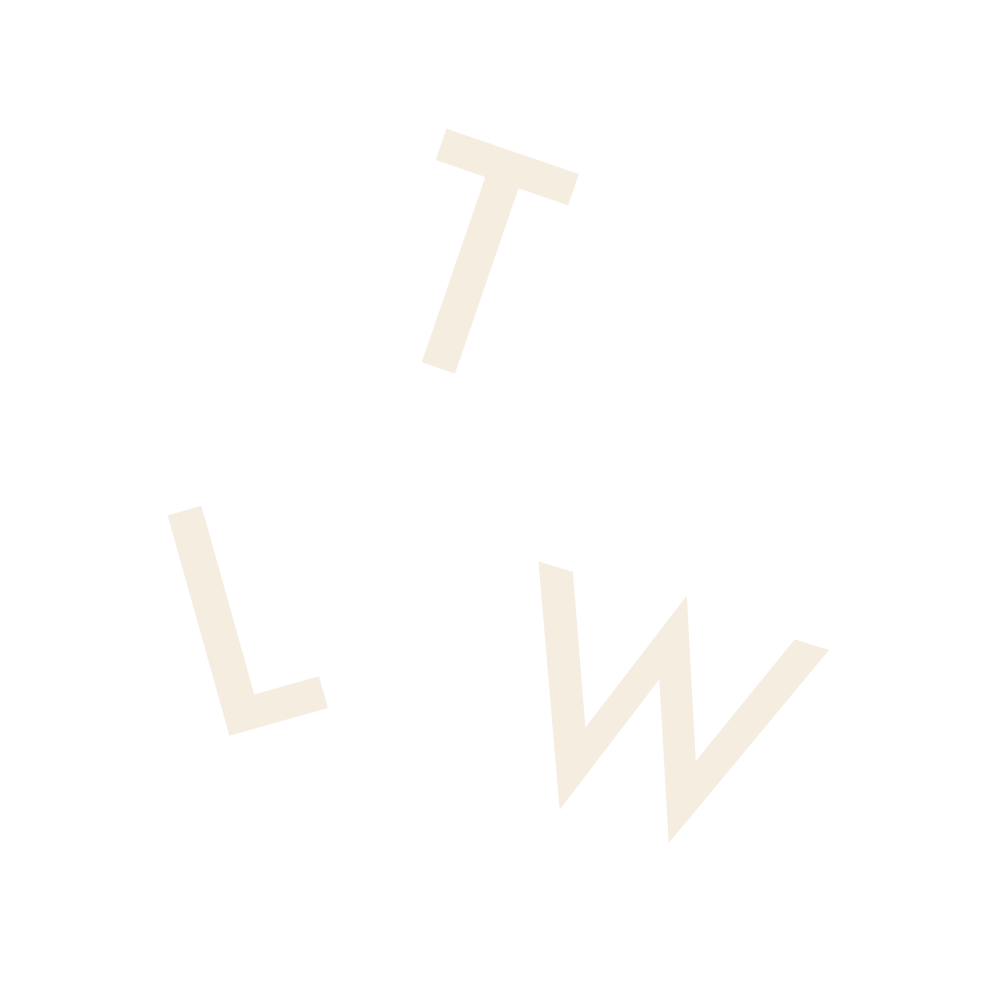おそらくこれが、THE LITTLE WHIM 年内最後の記事になる。そしてここには夫が登場する。今年は、彼のことを書き過ぎだ。
2020年、出だしこそは通年通り「どんな年になるかな」と広い世界を目指していたけれど、3月には「まさかこんな年になるとは」という驚きと混乱の兆しを見せていた。結局そこから、物理的にものすごくせまい世界を生きた。
夫は私にとっていつも身近な存在だけれど、今年は見事なまでに、顔を合わせて対話する数少ない貴重な一人となった。仕事で誰かに会うことも、友人とごはんすることも、お店やジムで会話することも、地下鉄で突然話しかけられることも、極めて少なかったから。そしてそれは、夫にとっても同じ。
家族ともほとんど会っていない。夫の家族は、みなニューヨーク及びその近郊に住むので、普段であれば顔を合わせることが多い。キプロス出身でギリシャ正教の義父をのぞき、イタリア系である義母の影響で全員カトリックで、大きく言えばみなキリスト教である。ゆえに、特に宗教的な意味を持つ日は彼らは当然のように一緒に過ごす。
思い返せば4月のイースター(復活祭)の頃、ニューヨークでの感染拡大を懸念し集まりを断念することになり、「仕方がないね」なんて言っていた。気づけば12月になり、クリスマスもあきらめることになるなんて、春の私たちは想像だにしていなかった。8年前から伝統の仲間入りした私にとっても、クリスマスを一緒に過ごさないことは違和感があるのだから、小さい頃から続き、たとえば義姉がボストンに進学してもカナダに引っ越してもずっと繰り返してきた家族の集まりが突然途絶えたのは、彼らにとって大きな穴だろう。
夫はずっと忙しくしていたので、クリスマス休暇は10日ほどとり、私も仕事を調整し、ゆっくりすることにした。画面越しに家族や友人たちと会いつつ、ほとんどは2人の時間。
クリスマス、夫と私は相変わらずブルックリンの小さなアパートの中で過ごしていた。それぞれが好きな服を着て、私は目元にお気に入りのアイシャドウをあしらいグリーンのアイライナーを入れた。みかんをつまみながら「ホーム・アローン 2」を観た。義母の作る料理は私たちには再現できないし、作ったところで食べきれない。ディナーはお互いが欲しているもののアイデアを出し合って、いつもより見栄えを気にしながらお皿に盛って、食べた。
夫は、夕方に Delirium Noel というクリスマス仕様のベルギービールを空けたあと、スコットランドは Islay という地域のスモーキーな香りが強いスコッチウイスキーを、ロックで飲み終えた。どちらも特別な時に飲むもので、そしてアルコールが強めだ。彼は酔っ払わないタイプだし、酔ったとしても少しぽわ〜っとし、話し方がゆっくりになる程度の平和なもの。しかしその夜は、歩くと足を少しもたつかせていたのが目に入った。今思えば、そこで彼が無意識の内にでも出しているサインにまで、気づけばよかった。
そのあと、些細なきっかけから小さな言い合いになった。どうでもいいことだったのに、なぜだか私はムキになり、引き際を逃してしまう。「クリスマスなのに、なんでそんな怒っているの?今年は2人だけなんだから、楽しく過ごしたいのに」と言う彼に、「クリスマスなのに、なんで酔っ払ってるの?今年は2人だけなのに、勝手なもんだよね」と私はいじわるな言い方で返す。すると、次の瞬間に彼は涙を流し始めた。私は仰天した。泣かせてしまった…!
普段は喜怒哀楽をあまり見せない彼が、泣いている。涙が次から次へとぼろぼろこぼれ落ちてくる。どうしよう …!思っていることを聞いてみると、こうこぼした。
「もう疲れた…。」
「かなしい。」
19年前に悲劇を経験した自分の街がまたしても悲鳴をあげる中、ベッドルームの小さなオフィススペースで、日中ランチをとる時間もままならない日もあるほど忙しく働いてきた彼が、疲れたと言っている。喜怒哀楽をあまり出さない人が、この10ヶ月異常な環境でがんばってきたのに、結局クリスマスもいつもと同じではなくなってしまったことに、哀しみを表している。
しかしそのあと、彼はこう続けた。
「だけど、君は東京に帰れず家族に一切会えていないのにね… 。自分が家族に会えなくてかなしいって思っていたけれど、君に『勝手なものだ』と言われてその通りだと思った。」
それを聞き、私もつられるように泣いてしまった。せまい空間で、いろいろな感情を共有してきたから、情が伝わるのもずいぶんと速くなったものだ。
そして何より、彼が言っているのは、今年私たちがまさに向き合ってきたことだと痛感した。今までにないほど、「人の痛みを理解しようとすること」を、よく考えた年だった。
感染症そのものとパンデミックは、不安、混乱や恐怖を引き起こした。そして自分自身の単位で感じるだけでなく、自分のまわりや大きな世界にいるほかの人たちが持つそれらについても知り、考えた。家族、友人、職場、コミュニティ、国、世界、そこかしこに及んだ今回のウイルスは、影響力が大きかったからこそ、その痛みには差が生まれた。義兄家族が感染し、友人が父親を失い、仕事上の知人は何人もが解雇になった。ブルックリンでは小さなレストランやお店が次々と閉店し、寄付や食料配布が盛んに行われた。アメリカの陽性反応率や死亡者数と合わせて、一時的解雇も含めた失業者数も深刻な状態が続いている。
「とはいえ私は恵まれているから…。」この言葉はどうも残酷で好きではないけれど、実際のところ、自分の状況に合っている。家も食べるものもあって、家族も安全に過ごしていて、仕事があって、笑う時間がある。つらいとか大変だと思うことはあっても、想像し得る最悪のケースではないというのは事実だ。
くわえて、今年は BLM の動きを目の当たりにした。人の痛みを理解し、ともに闘うアライシップもたくさん目にした。一方で、パンデミックの最中だったのもあってか、#BlackLivesMatter というこれ以上ないほどわかりやすい名を持つムーブメントにもかかわらず、多くの人々が差別などをベースにした個人目線の経験や見解も語り、人の痛み(だけ)ではなくそれぞれが自分たちの痛みを話す機会のようにもなっていた。広がりを見せるのはいいこととはいえ、あえての限定的意義が失われている現象には混乱した。
「人の痛み」を、そしてそれが「誰の痛み」であるかを理解することで見えてくる特定の特権。それらを意識することで、より色濃く見えてくるその痛み。「とはいえ私は恵まれているから…。」この視点があることで認識できる構造があるのだ。
私は、クリスマスが年末の一つの行事としてもてはやされがちな国で育った一人として、小さい頃から家族で過ごすからこそ大きな意味を持つクリスマスがかなわない夫の、痛みを感じた。夫は、そもそも家族と一切会えない時間が続き今後も不透明な私の、痛みを感じた。そして、お互いずっと疲れていた。結局、2人で子どものように泣きじゃくった。
夫はクリスマスライツが大好きだ。私たちが住むエリアは住宅が多いので、今年は控えめとはいえ、近所の家いえには色とりどりの光が灯る。「外を歩こうか。クリスマスライツを見に行こうよ」と私は提案する。「イーストリバー(マンハッタンとブルックリンを分ける川)まで行って、マンハッタンの光を見るのでもいいし」夫は少しだけ嬉しそうな顔になり、うなずいた。
重ね着し、ニット帽をかぶり、外に出る。一週間前に降った雪はほとんど消えていたが、空気は冷たい。マスクは顔を覆う防寒具の役割も果たす。いつも通りの2人に戻っていた私たちは、あれこれ指差し冗談を言い合いながら、外出を控えた今年、何度も何度も散歩した道を歩く。
イーストリバー沿いの公園にたどり着く。赤と緑に光るエンパイアステートビルディングが見えた。すると私たちの横をしゅっと何かが通り過ぎ、それと同時に懐かしい音楽が聞こえた。「あれ、スノーマンだよ!」と私はとっさに叫ぶように言った。
自転車に乗った若者が、スピーカーで、イギリスのアニメーション映画 “The Snowman” の曲を流しながら横を通り過ぎていったのだ。幼少期をイギリスで過ごした私は、クリスマスのたびにこの映画を観た思い出がある。音楽で伝えるストーリーと色鉛筆で描かれたようなビジュアルが優しい。セリフがないので、英語がわからなかった私も楽しめた。
自転車を早足で追いかける。川にせり出した桟橋のような通路にあるベンチに、その音楽の主がいた。”The Snowman” のテーマ曲は、最も盛り上がるところに差し掛かっていた。声をかけてみた。彼はイギリス人の父とアメリカ人の母を持つ、ロンドン出身のインディミュージシャン。アメリカではあまり知られていない、イギリスの子どもに愛されるこの映画について話しかけられたことに興奮していた。それぞれのバックグラウンドのこと、雪だるまと少年の映画のこと、パンデミックのことを話した。予定されていたツアーは、軒並み中止になったそうだ。寒い聖夜のブルックリン、自転車にまたがりスピーカーで音楽を流す彼の2020年は、決してハッピーなばかりではなかったと思うけれど、彼は笑顔だったし、私たちも笑顔にしてくれた。
高揚する気持ちとは裏腹に、イーストリバーの冷気で体は震えていた。「話せて嬉しかったよ」「メリークリスマス」と彼に別れを告げ、私たちはアパートに戻ることにした。帰り道、「今夜は “The Snowman” を観よう」と、私たちは同意した。
一緒にこの映画を観るのは2回目。数年前にダウンロード購入したものが残っていた。アメリカではあまり観られていない作品なので夫はなじみがなく、私にとっては小さい頃の思い出がいっぱい。30分ほどの短編の結末は切ないが、冒頭には夫の永遠のアイドルであるデイビッド・ボウイが登場する。
温めたオートミルクでホットチョコレートを作り、毛布にくるまって映画を観た。今でも大好きな作品だ。

未曾有の1年の終わりが近づく中、氷点下から身を守る場所があり、甘いホットチョコレートは温かく、隣に座る夫と体温を分け合うことができる。やはり、私は恵まれている。
そして、家族や友人と会えなくとも、新しいスタイルでの仕事のストレスが溜まっていようとも、体を寄せ合って座る私と夫は、それぞれの痛みを理解しようとする。そう、私たちは恵まれている。
「とはいえ私は恵まれているから…。」は、自分の核心を無視する意味でも、下を見て持つ感覚という視点からも、残酷さがある。しかしそうではなく、自分の痛みも、人の痛みも理解した上で、現実を受け入れることなのかな、とも思う。聖なる夜に、大切なパートナーとともに痛みを感じながら泣きじゃくったことで、なんだか腑に落ちた気がする。
今年も THE LITTLE WHIM を訪れてくださった方々、ありがとうございます。お住まいの場所ではまだまだ緊張が続くとは思いますが、どうか安全にそして健康にお過ごしください。